講演会「森と海と大地と」要旨
農業・林業・水産業、3つの一次産業に携わる“実践者”が「食と環境」をテーマにリアルを語る。
主催・登壇:株式会社東京チェンソーズ 代表取締役 青木亮輔ウミトロン株式会社 代表取締役 藤原謙オーガニックファーム所沢農人 代表 川瀬悟
日時:2025年8月24日 13時~15時30分
場所:所沢市民文化センターミューズ
【各講演内容】
■オーガニックファーム所沢農人・川瀬さん(農業分野)
川瀬さんは、地球環境に良いことをしたいという思いから、大地に根ざした野菜を育てる農業に従事しています。講演では、地球が過去5回の大絶滅を経験し、現在は人間活動を原因とする「第6の大量絶滅」がすでに始まっている可能性を指摘しました。ご自身のルーツである生態学の研究(横浜の緑地変化、台風後の森林変化など)の経験を活かし、有機農業を持続可能な地球環境との相互作用として捉え、多種多様な作物栽培に取り組んでいます。
現在の農業が直面する課題として、農地の減少(過去50~60年で2/3に減少)、農業従事者の高齢化と減少(65歳以上が7割)、そして異常気象(高温や豪雨)による作物への深刻な影響を挙げました。有機農業は注目され面積も増加しているものの、日本の農地全体に占める割合は0.6%未満と極めて少ないのが現状です。
川瀬さんの取り組みは、化学合成された薬剤や肥料を使わない「有機栽培」を基本とし、食品廃棄物や森の落ち葉、木枝などを堆肥として活用することで「土づくり」を「環境づくり」と捉えています。地域内のクラフトビール工場からの麦芽カスやカフェのコーヒー豆なども積極的に資源として取り入れ、廃棄物を資源化し、循環の輪を回すことで、持続可能な社会の実現を目指しています。また、ジビエソーセージの開発を通じて、野生動物による被害問題への貢献も行っています。
■株式会社東京チェンソーズ・青木(林業分野)
青木さんは、東京の93%が森林である檜原村を拠点に活動しています。日本が7割を森林が占める「森林大国」であるにも関わらず、多くの人工林が手入れ不足で荒れている現状に危機感を抱き、東京チェンソーズを設立しました。林業従事者も最盛期の10分の1に減少し、労働災害も多い厳しい環境です。
同社は「森の価値を最大化する」ことをテーマに掲げ、持続可能な森林経営を行っています。適切な間伐によって森を明るくし、草花、昆虫、鳥、広葉樹が育つ豊かな森を再生することで、土壌の保水力を高め、土砂災害を防ぐ効果を重視しています。
事業の特徴は、従来の市場出荷に頼らず、伐採した木材の根っこから幹、枝まで「1本丸ごと使い切る」ことで付加価値を高める点です。例えば、鍋敷きやアロマオイルのディフューザー、建築材として個性的な木材を活用するなど、多様なプロダクトを生み出し、無印良品やアットアロマといった企業とのコラボレーションも積極的に行っています。
さらに、山に暮らす人だけでなく、企業研修やワークショップを通じて都市の人々を山に呼び込み、「山と町街をつなぐ」「流域」の視点を重視し、都市部の住民にも森林の課題を「自分ごと」として捉えてもらえるよう、体験を通じて働きかけています。
■ウミトロン株式会社・藤原さん(水産養殖業分野)
藤原さんは元JAXAの研究開発員という異色の経歴を持ち、「誰のための研究開発なのか」という問いから、技術を人々の食生活に役立てたいと考え、水産の分野に転身しました。宇宙から見た地球が「水の惑星」であることに着想を得て、増え続ける世界人口の食料を確保する上で、海の資源を活用する水産業の重要性を痛感したといいます。
世界の天然魚獲量が30年間伸び悩む一方で、養殖生産量は2014年に天然漁獲量を上回り、今後も大幅な成長が見込まれています。養殖業は、畜産に比べてカーボンフットプリントが低く、飼料の肉への変換効率が高いという環境負荷の低い側面も持ち合わせています。
しかし、養殖業も課題を抱えています。最も大きいのは「資料原料となるタンパク質の調達問題」で、飼料の原料となる天然魚の乾燥粉末の価格高騰より、飼料代は生産コストの7割と経営を圧迫しています。また、赤潮や病気の発生、消費者のトレーサビリティや持続可能性への要求も高まっています。
ウミトロンはこれらの課題に対し、IoT、AI、衛星観測データなどの技術を活用して解決を目指しています。AIが魚の食欲を解析し、最適なタイミングと量で餌を与える「食欲解析技術」により、養殖期間を短縮し、飼料量を20%削減することに成功しました。これにより、生産コストの削減と、無駄な餌による海洋汚染の防止を実現しています。
藤原さんは、畜産や穀物の分野で進む「ドミナントデザイン」(効率の良い品種への集約化)が、今後魚の分野でも進むと予測し、品種改良や代替飼料の開発、大規模化といった技術革新が起こると見ています。一方で、生産者が自然災害や市場原理の中で高いリスクを負っている現状を問題視し、持続可能な生産システムの構築には、技術と合わせて「食に何を求めるか」という消費者の価値観の変化も重要だと提唱しています。
【3名によるトークセッション】
トークセッションでは、3名の講演者が互いの発表に対する感想や質問を交換し、それぞれの視点から持続可能性と第一次産業の未来について議論を深めました。
■農業分野・川瀬さんへの質問と意見
- 環境変動への対応(青木より): 林業が長いサイクルであるのに対し、農業は年単位の短いサイクルで環境変化(高温、豪雨)の影響を直接受けるため、「大変ではないか?」という懸念が示されました。
◦ 川瀬さんの考え: 農業の天候依存は「そういうもの」と認識しており、売上の変動は避けられないが、多品目栽培(150~200種類)によってリスクを分散し、どれかがダメでも他の作物が育つようにしていると説明しました。効率化を追求する慣行農業とは異なる有機農業の特性ゆえに、この多品目戦略が重要であると述べました。
- 有機農業の生産性(藤原さんより): 魚の養殖が効率化(ワクチン、投薬、添加物など)に向かう中で、ゼロから農業を始めるなら有機栽培と慣行栽培のどちらを選ぶか、また有機栽培で生産量を増やすことは可能かという問いが投げかけられました。
◦ 川瀬さんの考え: 魚や鳥の成長期間短縮・個体重量増加の背景にある技術に疑問を呈し、今後養殖が拡大すれば同様の問題が生じると予測しました。有機栽培での生産性向上は困難な目標だが、不可能ではないとし、環境負荷低減を目的とする生産者は支援されるべきだと述べました。また、生産量は栽培方法だけでなく環境要素も大きいため、有機栽培を単純に低生産性と結びつけるのは安直だという見解を示しました。
- 地域での有機農業の取り組み(青木より): 所沢市の「オーガニックビレッジ宣言」の内容や、有機農家の現状について質問がありました。
◦ 川瀬さんの考え: 所沢市は「オーガニックビレッジ宣言」を行い、学校給食での有機農産物の利用を積極的に推進していると説明。しかし、新規就農者の増加は全国的な課題と同様に少ないのが現状で、有機農家は全体で約15軒と、未だ珍しい存在であると述べました。
■林業分野・青木への質問と意見
- 全木利用の副次的効果(藤原さんより): 「1本ごまると使い切る」取り組みは手間がかかるが、利益以外の波及効果があるかという質問がありました。
◦ 青木の考え: 最大の副次的効果は「雇用創出」であると強調しました。従来の効率重視の林業では少ない人数で済むが、全木利用には皮むき、加工、営業など多くの工程が必要で、人口減少地域にとって貴重な雇用を生み出す。また、こうした取り組みは企業の関心や「関係人口」を増やし、地域の活性化につながると述べました。
- 新規事業立ち上げの苦労(藤原さんより): 新しい取り組みにおいて、パートナー探しや社内での苦労について質問がありました。
◦ 青木の考え: 大変だったとの認識のもと初期には社内メンバーから「本当に売れるのか」という懐疑的な声があったこと、そして1年目は売れずにチップ化したこともあったと打ち明けました。しかし、「1本丸まるごとカタログ」を作成し、建築家やデザイナーに地道に働きかけることで、徐々に理解と問い合わせが増えていった経緯を説明しました。
- 「流域」の取り組み(川瀬さんより): 都市部の人々に山の課題を「自分ごと」として感じてもらうための「流域」の具体的な取り組みについて質問がありました。
◦ 青木の考え: 自身が檜原村からゴムチューブに乗って多摩川を下り、羽田まで3日かけて移動した体験を語りました。この体験を通じて、川の水がどこで分水され、再生水が混ざり、どこにたどり着くかを実感したことが、都市の人々に山の水が街の暮らし(例:サントリーのビール)にいかに繋がっているかを伝える説得力になっていると述べました。将来的には、山と町街を繋ぐ「イカダ筏道」のようなリバートレールトレイルを復活させ、教育に「流域」の視点を取り入れることで、地域住民が環境保全を「当たり前」と感じる文化を醸成したいと語りました。
■水産業分野・藤原さんへの質問と意見
- 上流部(山・川)への思い(青木より): 山からの栄養流入とゴミの問題を挙げ、海から見た上流部への思いを質問しました。
◦ 藤原さんの考え: 近年、都市部の下水処理の高度化により、かえって川や海の栄養分が減りすぎ、海藻類が育たなくなる問題が生じていると指摘しました。一部自治体では、栄養塩をコントロールして流す実験も行われているが、因果関係の特定は難しいと述べました。多摩川が綺麗になったと言われる一方で、再生水が増えることで「無機質な水」が増え、アユなどの生態系に影響が出ている可能性も示唆しました。人間活動が環境に影響を与える以上、生物に必要な栄養量を人間がうまくコントロールしていく必要があるという見解を示しました。
- 事業軸の決め手(川瀬さんより): 養殖業における多岐にわたる課題の中で、事業の軸をどこに置いているのかという質問がありました。
◦ 藤原さんの考え: 事業の軸は「生産現場にいる生産者の声を聞くこと」であると述べました。生産者の要望をただ聞くのではなく、「なぜ困っているのか」を深く理解し、当事者の気持ちになって根本的な課題を解決するプロセスを重視していると説明。これにより、開発した技術やサービスが現場で真に活用されることを目指していると語りました。
- 技術導入の考え方(川瀬さんより): ロボット産業推進の例を挙げ、現場のニーズと技術開発の間に乖離があることについて、藤原さんの考えを求めました。
◦ 藤原さんの考え: 自身も当初「困っている人を助ける」という気持ちで現場に入ったが、逆に生産者に心配され、「助けられるのは自分だ」と気づいた経験を語りました。技術は現場の人を「エンパワー(力づける)」するものであり、彼らがやっていることをより上手に、負担少なくできるためのお手伝いという感覚で取り組むべきだと述べました。機械が故障した際に現場で直せるようなものであるべきだという見解も示しました。
【参加者からのQ&A】
- 青木への質問:全木利用の収益性
◦ 回答: 従来の市場出荷(100立方メートルで約100万円)から、加工やサービスを組み合わせた全木利用によって、売上は大きく向上しました。ただし、手間がかかるため利益率は4割程度であるものの、地域での雇用創出という大きな価値があることを強調しました。
- 3名への質問:エネルギー利用と環境負荷
◦ 川瀬さん(農業): 化石燃料由来のエネルギーをできるだけ使わず、有機物をいかに循環させるかに注力していると述べました。
◦ 青木(林業): 機械化は進むが、森林の整備や植林による二酸化炭素吸収量(カーボンクレジット)を価値化することで、エネルギー利用との相殺を目指していると説明しました。
◦ 藤原さん(水産業): 陸上養殖はエネルギー消費が大きいが、環境負荷を下げるために過度にエネルギーを使うと本末転倒になる懸念があるとし、エネルギーも含めた循環型の地産地消を考えるべきだと述べました。
- 3名への質問:ガソリン価格高騰と資材費への影響
◦ 川瀬さん(農業): 過去3年で資材費は年間2割増しとなり、全体で1.5~2倍に高騰しているが、売値は変わらずか下がる傾向にあるため、厳しい状況にあると述べました。
◦ 青木(林業): 燃料費の高騰は重機を使用するため負担となるが、同社は大規模な機械化を進めていないため、全体的な影響は大きくないとしました。一方で、通勤する社員のガソリン代負担は増えていると述べました。
◦ 藤原さん(水産業): 物流コストの大幅な上昇を指摘しました。生鮮品であるため冷蔵管理が必要で、保冷剤などのパッケージ材が魚の重量を超えることもあり、実質的な輸送コストが倍増する現状を説明しました。
【全体の共通した見解】
講演とディスカッションを通じて、3名の講演者から以下の共通した見解が示されました。
- 持続可能性と循環型社会の追求: 農業、林業、水産業のそれぞれの分野において、資源の枯渇や環境破壊といった現代の課題に対し、循環型アプローチによる解決の必要性を強く認識しています。
- 人間活動の環境への影響の自覚: 「第6の大量絶滅」の危機感や、都市からの排水が海洋生態系に与える影響など、人間活動が自然環境に与える不可避な影響を正面から捉え、その管理と共生の道を模索しています。
- 第一次産業の社会的基盤としての価値: 食料生産や資源供給を担う第一次産業が、社会の根幹を支える重要な役割を担っていることを再認識し、その価値を高めていくことの重要性を共有しています。
- 現場に根ざした革新と適応: 高齢化、人手不足、気候変動、コスト高騰といった各産業の具体的な課題に対し、川瀬さんの多品目栽培、青木さんの全木利用、藤原さんのAI活用など、それぞれの現場で独自の工夫と技術革新を通じて適応しようとしています.
- 都市と地方、山と海の連携: 「流域」という概念や、地域コミュニティとの連携、消費者との直接的な対話を通じて、異なる環境や立場の人々が繋がり、共に関心を寄せ、課題解決に取り組むことの重要性を訴えています。
- 「価値」の再定義と消費者意識の変革: 「早くて安くてうまい」だけでなく、「美味しくて、手間がかかり、それゆえに高価であっても、背景にある物語や環境配慮を理解して消費する」といった多様な価値観が受け入れられる社会への期待が語られ、生産者、消費者双方の意識の変化の必要性が示されました。
- 生産者のエンパワーメント: 技術やサービスは、現場の生産者が抱える課題を深く理解し、彼らの活動をより良くするための「お手伝い」や「力づけ」であるべきだという共通の認識を持っています。
この講演会は、第一次産業が抱える複雑な課題に対し、各分野の実践者がそれぞれの立場から実践的な取り組みと深い洞察を提供し、持続可能な未来への道筋を多角的に示す貴重な機会となりました。

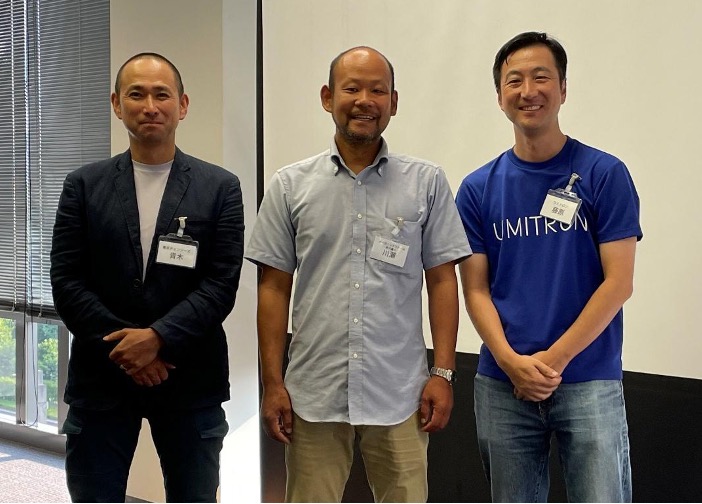 講演会終了後の主催者3名
講演会終了後の主催者3名